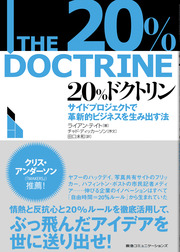20%ドクトリン サイドプロジェクトで革新的ビジネスを生み出す法
情熱は形にしなければ意味がない! 就業時間の20%を本来の仕事と異なるプロジェクトに使える「20%ルール」で、ぶっ飛んだアイデアを世に送り出せ! グーグルのGメール、写真共有サイトのフリッカー、NYの高校など豊富な事例を検証します。
- 書籍:定価1870円(本体1,700 円)
- 2013.06発行
まえがき
目次
まえがき チャド・ディッカーソン(エッツィCEO)
はじめに
創造する自由を与える精神/業界の中央舞台に躍り出る/20%ルールを革新に変える「20%ドクトリン」とは
1章 自分のかゆいところに目を向けろ
Gメールができるまでの暗くて長い闘い
不満が大きな製品を生みだす/まずは小さな試作品から始める/「正しい態度とは謙虚さ」だ/ほとんど全員がGメールを嫌っていた/必要なコードを4時間で書き上げた/既存のものを利用する勇気を持つ/製品発表のタイミングは慎重に/弱みを見せてサポートを得る/
2章 破産の危機を乗り越えて
制約が原動力となって生まれたフリッカー
早すぎたオンラインソーシャルゲーム/会社を方向転換する「ピボット」を目指す/政府からの思いがけないプレゼント/ネットでシェアする流れが追い風に/資金がありすぎることの弊害/
3章 プログラマーたちの祭典
ヤフー・ハックデイはこうして始まった
自分のアイデアをプレゼンする絶好のチャンス/コーディングが文化になる可能性/情熱に従えばクリエイティブになれる/集中力と競争心をあおる方法/「人事部に最も止められそうで賞」/おたく文化とロックンロール/文化の違いを超えて理解される/幹部社員にプレゼンできるチャンス/社内のプロセスを機能させる/プログラマーたちの運動会/
4章 教育の現場に20%ルールを持ち込め
NYの貧困地域に誕生した「自信」を育む高校
校長を舵を握る「CEO」に変革させた/文芸を重視する学校づくり/資金集めのための委員会を組織/視野を広げるために「外」へ連れ出す/「終わりに近づくことすらない仕事」
5章 市民が見せたジャーナリスト魂
報道を変えたハフィントン・ポストの素人記者たち
誰でも参加できる政治報道を目指す/帰属意識とともに目的意識を与える/魅力ある人員を引き入れるためにできること/コミュニケーションで定着率を高める/投稿のハードルを下げる試み/ボランティアに求める基準は緩めない/形式を打ち破ることを常に意識する/他との違いを際立たせる技術/草の根特派員のスターがものにした特ダネ/記者が入れないパーティーにもぐりこんだ/破壊的なものこそが成功だ/輝きを失って失速した/
6章 一流シェフの新たな出発
トーマス・ケラーが家庭料理に魅せられた理由
人に共感を与えることの重要性/即興でつくる家庭料理がメニューに/「思い出の味」で客を楽しませる/新しいルールが成功を導く/
おわりに
初期段階――アイデンティティの構築/中間段階――サポートをつかみ取る/最終段階――成長と決意
注
略歴
[著者]
ライアン・テイト Ryan Tate
ワイアードのシニアライター。アップサイド誌記者を経て、ビジネス2.0誌やサンフランシスコ・ビジネス・タイムズ紙、ゴーカー・ドット・コムなどに寄稿。本書が初の著作となる。
[序文]
チャド・ディッカーソン Chad Dickerson
ハンドメイドやヴィンテージの品を扱うマーケットサイト「エッツィ」のCEO。ヤフー・ディベロッパー・ネットワークのシニアディレクターだったときにハックデイを企画し、世界規模のイベントに育て上げた。
[訳者]
田口未和(たぐち・みわ)
1963年、北海道生まれ。上智大学外国語学部卒。新聞社勤務を経て翻訳業。主な訳書に『ビジネスについてあなたが知っていることはすべて間違っている』『悪魔の取引』(阪急コミュニケーションズ)、『ビジネスパーソンの時間割』(バジリコ)、『インド 厄介な経済大国』(日経BP社)など。
●ブックデザイン/竹内雄二